闇の中の光。あたたかい。
そして二日が過ぎた。
仕事を終えて、おれは帰りの電車の中で、半分眠る。隣に座った男から、嫌なにおいがして目が覚める。香水をつけるってのはどんな気持ちなんだろうか。あるにおいが気になるから、別のにおいをつけるという発想は、洋の東西を問わずあったみたいだが、どうにも馴染めない。最近は脱臭剤でも無香のものが多いから、おれと似たような発想の人間が多いのかと思ったが、よく考えてみるとおれは脱臭剤そのものを必要としていないので、あまり関係はなかった。とにかくにおいを消そうともがくことが、更なるにおいを生み出す結果になっているのはどういうことだろうか。
などと考えていると電車が新宿についた。大量のにおいが降りて、また多くのにおいが乗り込んでくる。ナフタリン、たばこ、酒、おっさんの加齢臭、若い女の甘いにおい、デブでわきが、ガキのミルクくささ。それらが混ざり合って、次第に感覚を麻痺させていく。鈍磨したにおいの神経が、やすらかな眠りにつくとき、おれはにおいの歴史の中で取り残された気持になる。どんなものを見ても、何かを思い出しているくせに、においで何かを思い出すことがない。五感の中では視覚と聴覚が強く、次いで触覚、味覚、嗅覚と続く。視覚、目、そうだ、おれは目で何かをおぼえようとする。つまりおれも、イマシロさん言うところの「視覚的人間」なのだ。
そんなおれが文字を書いていたのは、これは単に絵が下手だったというだけのことにすぎない。小学校のときに図画工作部にいて丸が描けなかった。線をひいていくと、どうしても「ゆるいうずまき」ができあがってしまうのだ。今思えば、定規やコンパスを使えばいいものを、なぜあの女教師はおれに丸を描かせようとしたのだろうか。あの女教師の流れるような長い髪を思い出す。よく張った太股を包む青いジーンズ。のびる材質のあのジーンズは、腰の線をくっきりと浮かびださせ、何も知らないはずのおれの神経をたかぶらせた。机につっぷしたまま、丸の描けないおれに、女教師が顔を近づける。長い髪がゆれて、机の上におちる。
「どうして描けないの」
「わかりません」
「描けるまで練習しなさい」
「わかりました」
放課後の図工室で女教師と二人、おれは延々白い紙に丸のような模様を描いた。いくら描いても丸にはならず、ゆがんだ円はうずまきに近づいていく。その時の窓からさす光、机の木の色合い、遠くの校庭で遊ぶ連中の嬌声、教卓で本を読んでいる女教師の組んだ足。においだけが、その記憶からすっぽり抜けていた。
強烈な視覚的人間が、絵を描く能力を奪われるとどうなるか。おれはその実験台なのかもしれない。だから文字に手を出した。そしておぼれ、飲み込まれ、吐き出された。文字はおれを弄んで捨てた。絵ではなく文章なら記憶を書き留めることができる、話すのは苦手でも、文章なら推敲ができる。他人と交流するために、文章ほどよい道具はない。そう思ったおれを救ってくれるはずの言葉達は、書けば書くほどおれから離れていった。
あれはいつのことだったか、文字が言うことを聞いてくれなくなったのは。
丸を描いているつもりが、ゆるいうずまきになってしまうように、おれの書く文章は横滑りを始めた。言いたいことがあったはずなのに、書いている最中に別のことへと変わってしまう。あわてて軌道修正をするが、もうもとには戻らない。最初に何を言いたかったかはわかっているから、横滑りを止めて、とりあえずの結論を書いて終わらせる。文字を踊らせる遊びが、いつのまにか文字に踊らされていることに気づいて慄然とする。誤解され、曲解され、文字数を減らしても減らしても横滑りは直らず。こんなはずじゃなかったのに、といやな気持になってブログを閉じた。
いまここに女教師がいたら、言うだろう。どうして書けないの? わかりません。書けるまで練習しなさい。わかりました。そしておれは丸を書きながら、おれの手をとって教えてくれたらすぐに描けるようになるのにと思うだろう。女教師がいつ、おれに丸を描かせるのをあきらめたのか、おれが図画工作部に行かなくなったのか、そのあたりの記憶はあいまいだ。探ればただ、ゆれる天井と、まわる床、そして窓の明かり、踊る黒い髪だけが見える。
いくつかの駅を過ぎる間、おれは中づり広告に目を通した。雑誌のあおり広告がざくざくと目に突き刺さる。赤と白、紺、黄色。とくに赤と白と黒の組み合わせが不愉快だ。書いてある事件の内容へのいらだちと勘違いしてしまうのではないか。そう思うとライターという職業もあわれなものだ。どんなに素晴らしい名文を書こうと、おれという人間一人が、色ごときに惑わされてしまう。この世界がすべて白黒だったらどんなにか素晴らしいだろう、ひとは文字を見てその内容だけに心躍らせる。だが色のない世界、おれには苦痛でしかない。文字はおれを助けてはくれなかった。何かを書こうとすると、必ず邪魔をした。三千文字しか書けなかったのは、おれが文字に勝てなかったからだ。おれは負けた、以来負けっぱなしである。
意地になるまでもなく、おれの手が一万文字を書こうとする気配はない。「どうだい、働いてるかい」じっと手を見れば、むしろ文字というものをこの手がどこかに書きつけるなんてことが、どだい無理な話だと思えてくる。
おれの手はマウスを握る形に変形している、掌の骨が卵型にゆがみ、小指から中指までの三指、そして親指は、ほとんど硬直している。左手はショートカットを押すために独立して動くが、それでも薬指でCtrlキーを押すおれの左手小指は、軽く曲がったまま九時間動かない。このまま本当に変形してしまえば、二度とこの右手はペンを握ることもできず、タイプすることもできないだろう。そのためにはあと何十年マウスだけを握っていればいいんだろうか。目の前にパソコンのないときもマウスだけは握っているべきだろうか。マウスを握ったままコンビニへいき、商品をクリック、ドラッグ、できるだろうか。できるか馬鹿。
コンビニのことを考えていたら、コンビニに行きたくなった。駅から家に帰る途中でコンビニへ寄ろう。おれの生活範囲はバイト先とコンビニと家に限られる。なんと心地よい三角形だろう。壊したくない。金があって困ることはないが、そのために時間を費やすことはない。
なんにせよざまあみろだ。何が一万文字だ。だいたい冷静になって考えてみれば、神様の言っていることの無茶さが見えてくる。おれがブログを書いていたころには、確かに一日三千字ほどの文字をタイプしていた。だがそれは何か意味のあることに限られていたのである。意味があったからこそ、横滑りする文字の反逆に疲れたおれは、書くことをやめてしまったのだ。
神は申された、意味のないことを一万文字書きなさい。確かに横滑りすることはないだろう。なぜならそれは全て横滑りなのだから。そんなものは、単なる苦行でしかない。なぜおれが文字を書いていたか、それは文字なら誰にでも通じるからだ。その「通じる」ということを失った文字に、興味はない。
同じ文字を使う相手には、ある程度ぶっ壊れた文章でも意味が通じる。これはおれにとって救いだった。しかも時代は進み、インターネットの上では誰もおれが丸を描けないことに気付かない。紙にペンで書いた文字を見れば、なんとなく絵が描けないということは推測がつくかもしれない。ゆっくり書けばどうにかなるレベルの文字ではないのだ。
「意味のないことでいいから毎日一万文字を書け」
いかにも神の言いそうなことだ。意味のないことを一万文字書いても、意味がないから誰も読まない。誰も読まないものを毎日一万文字も書けば金持ちになれるというのなら、毎日「うんこ」と三千三百三十三回書けばいい。最後の一文字は「う」で終わり、翌日は「んこ」から始まるのだ。
駅からおれのアパートに続く道の途中に、そのコンビニはあった。「あった」というのはつまり、今はない、ということだ。いつなくなったのだろう、今朝は寄らなかった、昨日の夜は? アパートに帰ってしまえば、通りの向かいにあるコンビニが近い。おれは疲れて一度寝て、夜中に起きて向かいのコンビニへ行ったのだ。なぜおれがコンビニを愛しているのかを、今まさに痛烈に気づいた。おれはひとに出会いたいのだ。だがそれは一度に数百円レベルの出会いでかまわない。
コンビニの店員は無愛想かもしれないが、確かにそこに生きていて、家に帰れば何かの生活をしているのだ。夜中のコンビニともなれば、長髪、金髪、刺青、ピアス、そのものではなく、それらの痕跡をみとめるだけで、おれは生き物にふれた感動を味わうことができた。店員だけではない、十二時ごろのコンビニに来ている男と女、午前二時ぐらいのコンビニへやってくる女の二人組、朝四時のコンビニで酔いを醒ますホストと派手な女。さまざまな客と、さまざまな店員が、まったく触れあうことなく同じ箱の中ですれ違って行く。おれにとってコンビニは、数百円で楽しめる動物園なのだ。
そのコンビニがいま、おれの生活範囲から消えつつある。もし三軒目が消えたら何をしよう、消えゆくコンビニをテーマに歌を作ってチャリティーコンサートを開こうか。そして貧乏になったマイケルジャクソンとコンビニトークショーをしよう。ふと見ると閉まったシャッターに「改装工事中」の張り紙があった。残念なことだが、チャリティーコンサートを楽しみに集まった子供たちへ謝罪のメッセージを送る羽目にならずに助かった。
家を通り過ぎて、通りの向かいにあるコンビニの、二件あるうちの遠い方へ行く。
おにぎりの棚で新製品を見つけた。イカ明太、これだ。定番のシャケとイカ明太、そして紙パックのカプチーノを持って、レジへ進む。おでんの水を入れ替えていた男が、おれに気づく。小さな声だ、いいぞ、目を合わせずに商品を手に取りバーコードを読み取る。ネームプレートにはキムラと書いてある。新人だ、初めて見る顔、声、仕草、そして名前。お前の名前はキムラ、わかるぞ、お前の名前がわかる。キムラ、お前はこんなところでレジを打っているような男じゃないんだよな。キムラ、子供のころ、お前の夢は何だった? 将来お前は何になりたいと思っていた? だけどキムラよ、お前のこの姿は美しい、よれよれの制服に疲れた無表情の顔、すべてが完璧にキムラ、お前という男の人生を表している。
キムラとおれが二人、真っ白な部屋で向かい合って立っている。決して目を合わせずに、商品だけが二人の絆となる、いまこの瞬間だけ、おれは貴様と向い合せになり、そしてその距離は限りなくゼロに近づく。レジの向こう側とこちら側は、厳密にいえば背中合わせで地球を包んでいる。おれとおまえは、世界を介してつながっているのだ。わかるかキムラ、これがコンビニユニバース理論といって、いまおれが適当に考えた。
「あ、これあっためてください」考えていることとは別に、いつもの指示が出た。
おれはあたたかいおにぎりが好きだ。コンビニのおにぎりは調整されているから、米のでんぷんを温めないでもうま味が出るようにしてあるらしい。だがおれはやはり、熱を通したときのでんぷんがもたらすあのうま味こそ、おにぎりを食べる醍醐味であるように思っているので、寿司系と「あたためないでください」という指示のあるもの以外は、ほとんどのおにぎりをあたためて食う。特に明太系のおにぎりをあたためたときのうま味は絶品だ。想像してほしい、炊き立てのご飯が茶碗に盛られ、その上にチョッと明太子の切り身を乗せる。その模造品が、ほんの百数十円で手に入るのだ。
「え、これですか」シャケにぎりを持ったまま尋ねるキムラ。
「いや、こっちも」とレジに置かれたままのイカ明太を指さすおれ。キムラは動かない。
まただ、前にもあった。今回はイカが原因だ。前は確か酢飯系だった。寿司ではなく酢飯系の場合はあたためるというま味が増すため、おれはよく温めてもらうのだが、その時は店長のモリキワが不審げな顔で「え、これですかぁ?」と言ったのでそれから二週間そのコンビニには行かなかった。何も客の言うことに反発したから怒ったというのではない、ただおれはおにぎりをあたためてもらいたかっただけなのだ。それなのになぜ、まるでおれが物分かりの悪いガキのように扱われ、怪訝そうに「これを?あたためるの?」といったような質問に晒されなければならないのだろう。何も整髪料のボンベをあたためろと言っているわけじゃないのだ。ただおれは、食べるために、そのおにぎりをあためてほしかっただけなのだ。
そうだ、酢飯をあたためて何が悪い。イカをあたためて何が悪い。明太子をあたためて何が悪い。
「え、でもこれ」
キムラ、お前におれの何がわかる。おれにお前の人生が何もわからないように、キムラ、お前にもおれがおにぎりをあたためる理由なんてわかりはしないだろう。だからキムラ、黙れ、それ以上おれの嗜好に踏み込まないでくれ。頼む。
キムラの顔に微笑みが浮かんだ。それは、無知なる者への憐みと慈愛に充ち溢れていた。
「温めない方が、いいですよ」
キムラ、お前全然わかってない。お前の趣味嗜好を押し付けないでくれ。お前はコンビニソムリエか、おれの唯一の楽しみを汚さないでくれ。何も努力なんてしなくていい、ただお前は「面倒くさい客だなあ」と思いながら、おにぎりをあたためてくれたらそれでいいんだ。なぜお前はおにぎりの美味しい食べ方をおれに教えようとするんだ。
キムラよ、なんだかおれはお前のことが好きになってきた。だからといって、おれも嗜好を曲げるわけにはいかない。今あたためてもらえば、家に帰って食べるときにちょうどよい温度になっているはずなのだ。すまないがキムラ、おれはお前を拒絶する。
「あの、いつもあっためてるんで」もちろん声は小さめだ。
「あ、はい」
キムラは意外にも、素直に電子レンジへ向かった。面倒くさい客だと気づいたのか、それともお前がおれじゃないことに気づいたのか。あたたまったおにぎりを持って、キムラがレジに戻る。
「袋は……」
「一緒で」
「いらしゃいませ」
「金を出せ」
黒いフルフェイスマスクの男がナイフを持ってキムラに言った。キムラから受け取った袋を持ったまま、おれは腰を抜かして倒れた。キムラ、言うことを聞け、すぐに金を出せ、店には保険がかかっているはずだ、お前が命を賭けるような仕事じゃないんだ。キムラ、お前の将来の夢は何だった?未来のお前は何をしているんだ、キムラ、やめるんだ、ナイフに手を出すな。
男のナイフが横に滑り、キムラは首を押えた。男はあいたままのレジから金を取り、隣のレジからも金を取った。慣れている、慣れているくせに。キムラの両手から、真っ赤な命がこぼれて消えた。
男が去り、数百年ぐらい経ってから、がくがくする膝を叩いておれは立ち上がった。レジの奥にキムラが倒れている。もう血は止まっている。目を伏せたまま、おれたちはあのとき、何か通じあえただろうか。キムラ、小太りで髪の薄いメガネ。
防犯ベルが鳴っている。おれはコンビニを出て家に帰る。数日後、誰かがおれの家のドアを叩くだろう、そのときまでキムラ、さよならだ。
家に帰って、少し冷めたイカ明太おにぎりを食べた。
少し冷めたとはいえ、やはりあたたかい方がうまい。明太の辛味が薄い気がするが、イカの質感は申し分ない。それよりも、おさえで買っておいたシャケのうまさに驚いた。単なるシャケなのに、粕漬け系の甘味と量感がある。さすが160円クラスは違う。キムラもシャケをあたためることには同意していた。シャケはあたたかい方がうまい、という共通認識があったのだろう。そのキムラも今はもういない、ほんの数十分前のことだった。フルフェイスマスクの黒、キムラの赤、蛍光灯の白、警察が来たらなんと言おう、びっくりしました、うん、これがいいな。
おにぎりとカプチーノが消費され、おれは歯を軽く磨いて電気を消す。
電気が消えたあとのもやもやした闇が好きだ。光のつぶがずらずらと流れ、不定形のかたまりになって闇の中をうごめいている。子供のころはそれを妖怪か何かだと思い込んでいた、蛇のような妖怪が、おれの部屋の隅には住んでいる。そう考えるだけで心が躍った。
眼の端に映るのはいつもうろこの立った太い蛇だった、それなのに、おれは夢で蛇を見たことが一度もなかった。夢に出てくるのはいつも現実に見る風景ばかりで、いわゆる「夢のような風景」を夢に見たことは一度もなかった。だから、寝入りばなに見るこの光のつぶが、おれは好きだった。明るい部屋では、それを見ることができない。光のささない真っ暗な場所に行くと、網膜が光とは別の何かを受け取って、それを見せてくれるように思った。実際は光の入力がないから、単なる電気信号のちらつきを光だと御認識しているだけなのかもしれない。それでもその蛇は、おれの部屋の隅でうごめいていた。
ここに越してから、アパートに面した通りは、朝まで車の途切れることがないから、オレンジと白の明かりをふせぐために、おれは分厚いカーテンを買った。
毛布のように分厚いカーテンを、と、おれは店員に注文した。それはあたたかい日で、おれよりもはるかに身長が高く、若そうに見える女の店員は、にっこりと笑ってサンプルの入ったファイルを差し出した。来年新卒の研修生なのだろう、初々しいその丁寧な対応が心地よい。さらには、その掌の大きさに、おれは興奮を隠せなかった。寸法にして数センチ、体積の違いがおれの性欲をかきたてる。運動をやっていたのだろうか、骨格もしっかりとしていて、筋肉もついている。押しつぶされたい、この掌に包まれたい。ファイルに貼られたサンプルをしめすその指の太さに、頭がクラクラした。もう一度顔を見る、すっかり補正がかかってしまって、まるで天使のようだ。おれは女の顔をまともに見られない。
「あ、あの、それで、はい」と要領を得ないことをつぶやきながら、おれは適度に分厚いカーテンを選んだ。ああ、でかい、でかいぞ、なんともはや。
古来、女は大地であった。そう言ったやつの顔をおれはひっぱたいてやりたい。ばか!愛してる!そう言って抱きしめてやりたい。自分より小さな女に欲情する男の気がしれない。あんな奴らは全員ロリコンの変態で、家には幼女ポルノがたくさん置いてあるに違いない。いや、百歩譲っても、小さくてやせ細った女しか女と認めないような男はつまり、人間を外見で判断するという愚行を間違いとも思わない悪辣非道な輩なのである。
「お前だって外見で判断してるではないの」と神が笑った。
電気が消えたあとのもやもやした闇に、いやらしい笑い顔が浮かんでは消える。おれは ぐちゃぐちゃになった毛布を広げて、その中にうずくまった。明日から旅に出よう、このどうしようもない循環を断ち切ろう、そして神様と一緒にどこか遠くへ消えてしまおう。おお、おれは神殺しの男、ラララ。眠れない。
「旅に出るとすれば、出雲がいいなあ、私の故郷だ」
「へえ、神様って日本の神様なのか」
「何だと思ってたんだ」
神様は心底、心外そうな声で答えた。おれはなんだかおかしくなって、笑いだした。そりゃそうだ、こんなごみためみたいなところに来るのは、日本の神様ぐらいのもんだろう。
「それで、神様は何の神様なんだ」
「今、名前を言うのははばかられるな」
一瞬頭に「小説の神様」の名が浮かんだが、すぐにその妄想はかき消えた。何しろこいつは突然現れて「自己啓発本を書いて儲けよう」ともちかけてきたのである。どれだけ詐欺師的な現れ方が世の中にあるとしても、これほど詐欺師的な現れ方はほかにないだろう。まず儲けようという題目が詐欺以外の何物でもない。儲け話が儲かるのは、それを誰も知らないからである。もし誰かに「誰も知らない儲け話をあなただけに教えよう」と言われたときには、三つの理由を想定するといい。ケツを貸りたいか、ケツを貸したいか、お前をカモりたいか。
次に自己啓発本である。おれも数年前はずいぶんとその手の本を読んだものだが、これを書くのには才能がいる。どんな才能かというと、それは「非、実験精神」とでも言うべきものである。
自己啓発本には二種類ある、ひとつは過去の成功例から成功の法則を導き出したもの、もう一つは自分でやったもの。自分(もしくは誰某)は、このような方法で成功した、だからお前もそれをやれ、というわけで、まるでこれだけ聞くと「実験」に成功した方法を皆さんに教えますよ、というふうに感じてしまう。だが思い出してほしい、誰も知らない儲け話をあなただけに教えるとき、ひとは何を求めているのかを。
ある成功例は、ひとつの成功例に過ぎない。それがわかっているからこそ、広告はすべて「この本を読んで成功しました」という読者の感想文であふれかえっているわけだ。つまり、それがどのような成功例であれ、誰にでも当てはまるかどうかは、やってみなければわからない。
これが科学の実験であれば、何度も追従実験の行われたものなら、その実験を行って同じ結果が出る確率の高低もわかるだろう。しかし、相手は人生である。そんなもん思い込みでどうとでもなるし、何をしたってどうしようもない時もある。
ともあれ、この神様、今おれの頭の中で自慰の邪魔をしているこの神様に関して言えば、古今東西歴史上どこを探してもいないくらい最悪の詐欺師である。何しろ成功例の一個もないことを、おれにやれと言うのだ。
おれはとにかく自慰がしたくてたまらないので、考えるのを中断し、妄想を再開した。家具売り場で会ったでかい女のことを思い出す。まだ若く、肌のつやもいい。どんなシチュエーションにしようか、おれが上司で、相談に乗っているうちに、というのはどうだろう。裏の資材置き場とか、そういうところで話を聞きながら、なんとなくいい感じになってくるってのは、どうだろう。
「わかった、じゃあポルノにしよう、ポルノでいいから一日一万文字」
「何で一万文字なんだ、何でそれにこだわるんだ、どうしておれの自慰を邪魔するんだ」
「一度にいくつも質問するな、ただ一言、どうしても言いたいことを言えばいい」
「消えろ、お願いだから頭の中から消えてくれ、おれに自慰をさせてくれ」
「すればいい、別に私は困らないから、キリスト教ではないから自慰が罪ということもないし」
「困るんだ、やっている最中にお前が話しかけてくると、その、すごく困るんだ」
おれは暗闇の中、起き上がり、電気をつけた。
山のようなごみ袋が消えていた。
「見ろよ、一晩だ。お前が話しかけ続けるから眠れなくて、昨日一晩でゴミを全部捨ててしまった。一昨日まで部屋いっぱいにあったのに、分散して捨てるのにどれだけ歩きまわったと思う? おかげで今日の昼は眠くて仕方なかった、仕事にならなかった」
「でも、住みよい環境になっただろう?こうして人間はより良い環境で自己を啓発しながら生きていけるのである」
頭の中に虫が入り込んで、光をもとめて飛び回っているみたいだ。神様、お前にはわからないかもしれないが、直したってどうしようもないやつがこの世にはいるんだよ。ファーブル琉・肉バエの集め方。さかさまにした籠の中に肉をつるし、下が開くように設置する。肉のにおいにつられてやって来たハエは、下から入り込んで肉へとりつく、しかしハエは上に向かって飛ぼうとし、籠の下が開いていることに気付かない。
籠の下が開いていることに気付かない。
底の抜けたバケツで水をくむようなものだ。そして、その穴は宗教も科学も埋めようがないのである。トタンの壁が小便で腐っていくように、最初は小さな穴だったものが、次第になんだかわからないうちに広がって、いつの間にか壁よりも穴の方がでかくなってしまう。空虚な穴があって、その中に壁だった境目がある。
「どうしておれなんだ、もっとやる気のある若いやつに出てやれよ」
「そういうのは他の神様がやってる、私のは違うんだ」
全身に鳥肌が立った。何がおかしいか、うまく組み立てられないが、違和感の原因に気づいたのだ。なぜ、幻覚なのに、こいつの顔がおれには見えないのか。なぜ、こいつはおれに文字を書けと執拗に勧めるのか、なぜおれなのか。それらの「答え」ではなく答えを導き出すためのルートが少しずつ頭の中でカチカチと音をたてて組みあがっていく。ぼんやりと見えるその答えに近づこうとすると、全身の細胞が悲鳴を上げる。
「毎日、一万文字」
「それってお教か何か?」
「編集するんだ」
「おれたちは正義だ」
仕事ばかりで遊んでないと、ジャックはそのうち気が狂う。
「お前は、文字の」
絶対に、毎日一万の文字を書いてはいけない。
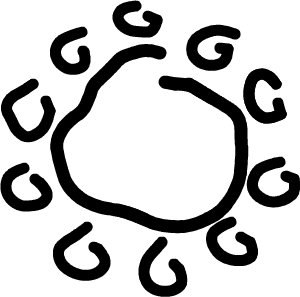
つづく
http://d.hatena.ne.jp/./screammachine/20080315#p1